刑事裁判 [けいじさいばん]
- 意味
- 刑事裁判とは、犯罪を犯した疑いのある者(被疑者・被告人)について、事実関係を明らかにし、適正な刑罰を決定する司法手続きです。交通事故においても、被害者が死亡したり重傷を負ったりした場合や、飲酒運転や逃亡などの法律違反が認められた場合は刑事裁判へと発展することがあります。
- 解説
捜査~刑事裁判の流れ
刑事裁判は、以下の手順で進行します。
警察による捜査

犯罪や事故が発生した(と思われる)場合、まずは警察が事実関係を調べる捜査を行います。
交通事故であれば、事故現場を詳細に調査し、事故発生時の状況を確認する「実況見分」という手続きを実施します。また、関係者や目撃者からの事情聴取を行い、その内容を供述調書としてまとめます。
捜査段階で罪を犯した疑いがある者は「被疑者」と呼ばれ、逃亡や証拠隠滅などのおそれがあると警察が判断した場合、被疑者は逮捕されて身柄を拘束されます。逮捕された場合、警察は最長48時間の取り調べを行い、証拠が十分であると判断すれば、被疑者の身柄を検察官に送致します。
一方、被害の程度が軽微な事故や事件では、検察官への送致は不要と警察が判断し、「微罪処分」として処理されるケースがあります。微罪処分の場合は起訴されることはなく、罰金などの刑罰も科されず、前科もつきません。
検察による捜査と起訴・不起訴の判断
検察官に事件が送致されると、検察官が最長24時間の取り調べを行います。その結果、被疑者に刑罰を科す必要があると検察官が判断した場合、被疑者は「起訴」されて刑事裁判へと進むことになります。
起訴とは、検察官が裁判所に刑事裁判を開くように求めることです。起訴された時点で、被疑者は「被告人」と呼ばれます。日本の刑事裁判では、起訴された事件のほぼすべてが有罪判決となるため、起訴されることは重大な意味を持ちます。
一方、刑罰を科すほどの事件ではない、あるいは十分な証拠がないと検察官が判断した場合には「不起訴」となります。不起訴処分の場合は、刑罰が科されることはなく、前科もつきません。
もし、24時間の取り調べで起訴するかどうかを検察官が決定できなければ、被疑者の身柄を引き続き拘束するため、裁判官に「勾留」を請求します。勾留が許可された場合、原則として10日間、最長で20日間、被疑者の身柄が拘束されます。
公判前整理手続
起訴後は裁判(公判)へと進みますが、公判の前に「公判前整理手続」が行われることがあります。
公判前整理手続とは、刑事裁判をスムーズかつ効率的に進めるため、公判に先立ち、裁判官や検察官、弁護人が話し合いを行い、審理すべき争点(事件で特に問題となる点)や証拠の範囲をあらかじめ整理することです。
特に、重大な事件や、争点が複雑な事件の場合、裁判が長期化することを避けるため、この手続が行われます。
公判

「公判」とは、刑事事件について法廷で公開の裁判を行い、被告人の有罪・無罪や刑罰を裁判所が決定するための手続きのことです。
公判では、検察官が収集した証拠を法廷で提示し、被告人や弁護人がその証拠に反論したり、証拠を提出したりします。また、必要に応じて証人尋問が行われ、裁判官がこれらの内容を踏まえて判断を下します。
殺人や強盗致死傷など、重大事件は「裁判員裁判」として裁判が行われます。裁判員裁判では、法律の専門家である裁判官だけでなく、一般の国民からランダムに選ばれた裁判員も審理に参加し、共に被告人の罪を判断します。
交通事故においても、被告人が危険運転致死などの罪に問われている場合、裁判員裁判の対象となります。
判決
裁判官は、公判で提出されたすべての証拠や証人の証言を精査したうえで、被告人が罪を犯したかどうか(有罪か無罪か)を判断し、「判決」を言い渡します。
有罪判決が言い渡された場合、裁判所は懲役刑や禁固刑、罰金刑などの刑罰が科されます。これにより「前科」がつくことになり、その記録は警察や検察、市区町村に保管されます。
一方、無罪判決の場合は、被告人は刑罰を科されず、前科もつきません。
控訴・上告
判決に不服がある場合、被告人や検察官は、上位の裁判所へ再審理を求めることができます。これを「控訴」(第一審→第二審)、「上告」(第二審→第三審)と呼びます。
控訴審では、一審における事実認定や量刑の妥当性が改めて整理され、新しい証拠が提出されることもあります。また、控訴審の結果、一審の判決内容(量刑)が変更されることもあります。
上告審では、控訴審のように改めて事実関係を詳しく審理するのではなく、主に法律の解釈・適用に誤りがないかを審査します。そのため、新たな証拠を提出したり、事実関係を再度詳しく検討したりすることは原則としてありません。
もし、法律的な判断に誤りが認められれば、控訴審の判決が破棄され、判決内容が変更される場合もあります。
通常の裁判が行われるケース
これまでご説明した裁判の流れは、「過失運転致死傷罪」「危険運転致死傷罪」など、被害の程度が大きな事故や、重大な交通違反があった場合に適用されます。
- 過失運転致死傷罪
- 自動車の運転に必要な注意を怠って人を死傷させた場合は、過失運転致死傷罪が成立します。刑罰は、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金です(自動車運転処罰法第5条)。
- 危険運転致死傷罪
- たとえば、飲酒運転や薬物を使用しての運転、極端なスピード違反など、過失運転よりも悪質な運転により人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が成立します。刑罰は、被害者が負傷した場合は15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上の有期懲役です(同法第2条)。
略式裁判が行われるケース
検察官が起訴するべきと判断した場合でも、必ずしも通常の手続きが行われるわけではありません。
刑罰が100万円以下の罰金または科料に相当する事件の場合、「略式裁判」という簡易的な手続きが用いられるケースがあります。
略式裁判では、検察官が裁判所に提出した書面および証拠資料のみによって審理が行われます。通常の刑事裁判とは異なり、非公開の場で審理が行われ、比較的短期間で手続きが終了します。
被疑者・被告人に認められる「黙秘権」
被疑者や被告人には、取り調べや裁判の場で、話したくないことは話さなくてもよい権利が認められています。この権利を「黙秘権」と呼び、黙秘したことを理由に判決が不利になってしまうことはありません。
黙秘権を行使する場合、自分が不利になる内容について話さない「一部黙秘」と、まったく話さない「完全黙秘」の2種類があります。そして、黙秘権を行使することで、不正確または自分にとって不利な内容の供述調書が作成されてしまうリスクを軽減できます。
事故当時の記憶が曖昧な状態で取り調べを受けた場合、事実とは異なる内容を話したとしても、供述調書として記録されます。この点、取り調べで黙秘することで、不正確な供述調書が作られなくなるのです。
ただし、黙秘を続けることで、取り調べに協力しないとして身柄を拘束される期間が長期化するおそれがあります。そのため、取り調べの受け方について、弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士に刑事裁判の対応を依頼する最大のメリットとは
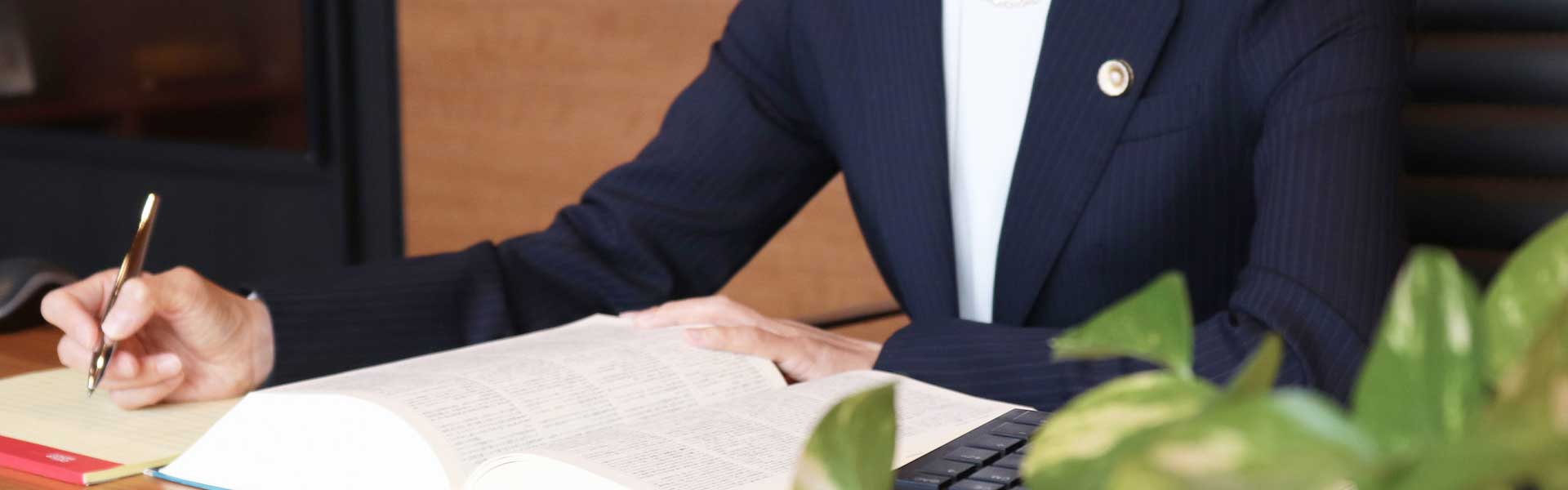
刑事手続きは専門性が非常に高く、その後の人生に重大な影響を与えます。そのため、手続きの進め方を誤れば、本来受ける必要のない著しい不利益を被るおそれがあります。
弁護士に刑事裁判の対応を依頼する最大のメリットは、専門的な法律知識と経験を活かし、依頼者の権利を適切に保護できる点にあります。
特に交通事故による刑事事件の場合、事故状況や証拠の評価が重要な争点となります。弁護士が介入することで、捜査段階から適切な対応が可能となり、不適切な供述調書の作成や不利な証拠の提出を防ぐことができます。
また、逮捕・勾留が行われている場合には、早期の身柄解放に向けて弁護活動を行い、依頼者の精神的・身体的な負担を軽減することが可能です。
さらに、公判が開始された後も、弁護士がいれば効果的な弁護戦略を立案し、適切な証拠提出や証人尋問を通じて、無罪判決や刑の減軽を目指すことができます。特に裁判員裁判では、法律的な主張を裁判員にわかりやすく伝えるスキルが求められますが、この点においても弁護士のサポートは非常に有益です。
加えて、弁護士による示談交渉により、被害者との間に示談が成立すれば不起訴処分の獲得や刑の減軽など、刑事裁判の結果を左右する影響を与えることができます。
このように、刑事裁判に発展した場合、弁護士にその対応を依頼することは、非常に重要であり、欠かせない選択肢といえるでしょう。
用語を探す
キーワードで探す
交通事故に関するキーワードを入力して、該当する用語があるか調べられます。

