刑事事件 [けいじじけん]
- 意味
- 刑事事件とは、法律で定められた犯罪行為が行われた場合に、捜査機関(警察や検察)が介入し、刑事責任を問う手続きが進められる案件を指します。交通事故も、被害の程度や違反内容などによっては、民事事件だけでなく刑事事件として扱われることがあります。
- 解説
交通事故の加害者になってしまうと、次の3つの責任が生じる可能性があります。
- 民事事件として、被害者から慰謝料などの損害賠償金を請求される
- 行政事件として、行政処分が課される
- 被害者を死傷させる人身事故を起こした場合、刑事事件としても扱われ、起訴されて有罪判決を受けると懲役や罰金などの刑事罰を受ける
この記事では、特に②と③について解説していきます。

事故を起こした場合の行政処分
そもそも行政処分とは、行政機関が法令にもとづき、国民に義務を課したり、権利を付与する行為です。そして、交通事故の場合、公安委員会が道路交通法などにもとづき、運転者などに処分を行います。
行政処分の種類
交通事故を起こした場合に課される行政処分は、主に次の2種類があります。
- 免許停止処分
- 一定期間、運転免許の効力が停止される処分です。停止期間は事故の状況や過失の程度によって異なりますが、30日~180日程度が適用されるのが一般的です。俗に「免停(めんてい)」と呼ばれます。
- 免許取消処分
- 特に重大な事故や悪質な違反があった場合、運転免許が取り消されることがあります。免許取消を受けると、一定期間(欠格期間)経過後でなければ再取得ができません。欠格期間は1年~10年と幅広く、事故の内容によって決定されます。俗に「免取り(めんとり)」と呼ばれます。
行政処分の基準
運転免許には、違反や事故に応じて点数が加算される「累積点数制度」があり、点数が一定の基準を超えると、免許停止や取消の対象となります。20点以上は免許取消処分の可能性が高いです。
免許停止の場合、その期間は、累積点数が6~8点の場合は30日、9~11点は60日、12~14点は90日となっています。また、過去に行政処分を受けた前歴があれば、点数に応じた停止期間はさらに長くなります。
軽微な違反(例:速度超過、信号無視) 1~3点 相手に3週間未満の治療を要する怪我をさせた人身事故 6~13点 相手に3週間以上の治療が必要な怪我をさせた人身事故 13~20点 死亡事故 20点以上 免許停止や免許取消は、警察が関与するため、刑事事件と思われがちなのですが、そうではありません。次に、交通事故における刑事事件について解説していきましょう。
事故を起こした場合に成立する刑事罰
人身事故を起こして刑事事件となった場合、どのような犯罪が成立するでしょうか。犯罪の種類やその刑罰について詳しく説明します。
過失運転致死傷罪
自動車の運転に必要な注意を怠って人を死傷させた場合は、過失運転致死傷罪が成立します。刑罰は、7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金です(自動車運転処罰法第5条)。
危険運転致死傷罪
たとえば、飲酒運転や薬物を使用しての運転、極端なスピード違反など、過失運転よりも悪質な運転により人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が成立します。刑罰は、被害者が負傷した場合は15年以下の懲役、死亡した場合は1年以上の有期懲役です(同法第2条)
轢き逃げ(報告義務違反・救護義務違反)
交通事故が起きた場合、運転手や同乗者には、警察に通報する「報告義務」や、負傷者を救護する「救護義務」が課されます(道路交通法第72条1項)。
相手を死傷させたにもかかわらず、通報や救護せずに立ち去る行為はひき逃げにあたり、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪に問われるだけでなく、それぞれの義務に違反することになります。
刑罰は、報告義務違反が3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項17号)、救護義務違反が10年以下の懲役または100万円以下の罰金です(同法第117条2項)。
人身事故でなくても刑事事件になるケース
交通事故で人を死傷させなかったとしても、刑事事件になる可能性はゼロではありません。たとえば、次のようなケースです。
あおり運転(妨害運転罪)
2021年11月10日に公布された改正道路交通法により、あおり運転(妨害運転)に対する罰則が新たに作られました。
あおり運転は、車間距離を詰めた接近、急な進路変更や蛇行運転、急な加減速や幅寄せなど、ほかの車両の交通を妨害するさまざまな行為が該当します。そして、死傷者がいなくても、あおり運転に該当する行為をするだけで、刑事事件となる可能性があるのです。
あおり運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金(同法第117条の2の2第8号)で、著しい交通の危険を生じさせた場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金(同法第117条の2第4号)です。

運転過失建造物損壊罪など
人の死傷がなく、物だけが傷ついた物損事故は、多くの場合は刑事事件にはなりません。しかし、飲酒運転、無免許、逃走など、悪質な違反行為による物損事故は、刑事事件として扱われる可能性があります。
さらに、運転者が必要な注意を怠り、または重大な過失により他人の建造物を損壊したときは建造物等損壊罪が成立する場合があります。刑罰は、6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金が科されます(同法第116条)。
交通事故を起こしてしまったら、弁護士にご依頼ください
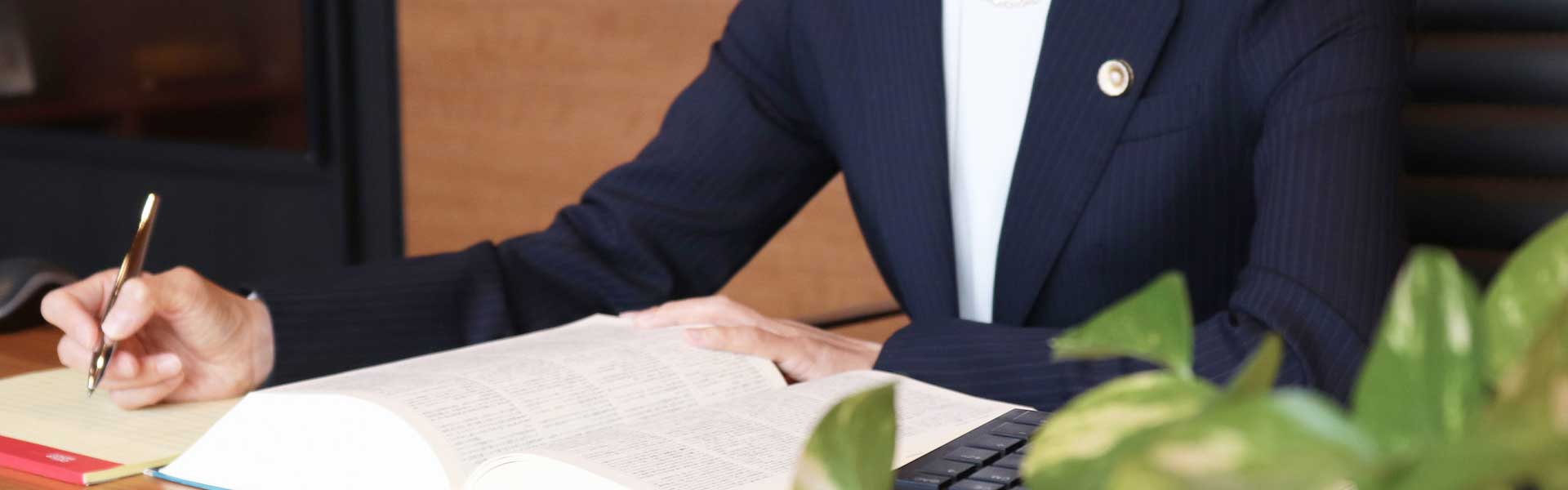
交通事故を起こして被害者を死傷させてしまい刑事事件になった場合、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は速やかに被害者との示談交渉に着手します。示談が成立すると、次のように、重大な結果が生じる可能性が大幅に低減します。
- 逮捕勾留された場合に、早期に身柄が解放される
- 不起訴処分により前科がつくのを回避できる
- 有罪判決を受けても、執行猶予処分など刑罰が軽減される
また、交通事故が刑事事件になると逮捕されると思う方も多いでしょうが、必ず逮捕されるというわけではありません。「在宅事件」として、逮捕されずに捜査が行われるケースもあります。
ただし、被害者が重傷を負ったり亡くなったりした場合や、悪質な違反によって事故を起こした場合、逃亡や証拠隠滅の危険性があると警察が判断した場合などは、逮捕される可能性が高いです。
逮捕された場合も、できるだけ早く弁護士に相談し、対応を依頼しましょう。
逮捕されてから約3日間に加害者と接見できるのは弁護士だけです。そして、この期間中の取り調べで作成される調書の内容によって、今後の手続きが不利になるケースが少なくないため、適切な対応が求められます。
弁護士に依頼すればすぐに加害者と接見し、今後の手続きについて説明やアドバイスをしてくれるため、取調べにも適切に対応できるようになるでしょう。
- 関連する用語
- 刑事裁判[けいじさいばん] 刑事記録[けいじきろく]
用語を探す
キーワードで探す
交通事故に関するキーワードを入力して、該当する用語があるか調べられます。

