カルテ [かるて]
- 意味
- 医師が診察の際に作成・記録する診療の記録であり、「診療録」とも呼ばれます。交通事故においては、損害賠償の請求や後遺障害の認定申請などで、特に受傷内容や事故とケガとの因果関係などを詳しく証明する際に重要な資料となります。
- 解説
0. カルテとは
カルテとは、医師が行うすべての医療行為において、患者ごとに管理される診療の記録のことです。ドイツ語の「Karte」に由来しています。
医師法では、医師に対してカルテを作成する義務を定めており、また、診療が完結した日から少なくとも5年間の保存義務があることも定めています(医師法第24条)。
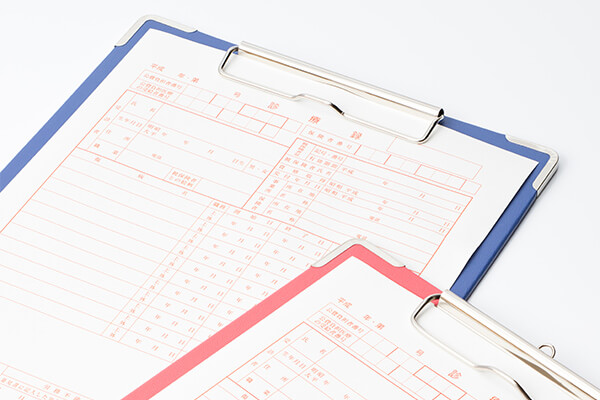
- 第二十四条
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 - 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
引用元:医師法
近年は、業務効率化や医療安全の向上、スピーディな情報管理の観点などから電子カルテの普及が進んでいます。
そして、カルテには、次のような情報が時系列で記録されています。カルテを確認することで、診断書や診療報酬明細書(レセプト)に記載された情報の詳細について把握することができます。
- 氏名、年齢、既往歴などの基本情報
- 初診日および事故申告の有無
- 受傷部位や症状の詳細
- 検査結果(X線やMRIなど)
- 処方された薬や治療内容
- 症状の変化や通院頻度
- 医師による診断名・所見
交通事故の被害に遭ったとき、医学的に争いがあるような場合、ケガの内容や程度を詳しく証明するための資料として、カルテの開示を受けた方が望ましい場合があります。
1. 交通事故の被害者がカルテを入手すべきケース
交通事故の被害に遭ってケガを負ってしまった際、加害者側に対して損害賠償を請求することができます。
また、治療を続けても何らかの後遺症が残る場合、後遺障害の等級認定を受けることで、慰謝料や逸失利益を請求することができます。認定を受けられなかったり、認定された等級に納得できなかったりする場合は、異議申立てにより再審査を求めることもできます。
これらの手続きでは、ケガの内容や程度、事故との因果関係などについて、医学的な資料にもとづいて客観的に立証することが求められます。そのため、被害者の治療に関する詳細な情報が記載されたカルテが、証拠として重要な役割を果たす場合があります。
特に次のような場面では、カルテの開示が求められるでしょう。
- 後遺障害の等級認定を被害者請求で申請する場合
- 後遺障害の等級認定では、治療の内容や期間、治療による症状の変化など、診療の経過が重視されます。等級の認定を受けるのが難しいと予測される場合、被害の程度に見合った認定を受けるため、診療の詳細な経過を客観的に証明できるカルテが必要となるケースがあります。
- 後遺障害等級に対する異議申立てを行う場合
- 認定を受けられなかった場合や、認定された等級に納得がいかない場合、異議申立てを行うことができます。認定結果を覆すための証拠として、カルテの記載内容を活用することがあります。
- 加害者側と賠償金額で大きく対立する場合
- 加害者側の保険会社と賠償金額で大きく対立すると、裁判に至るケースがあります。「事故とケガとの因果関係」や「ケガの重症度や治療内容」などを立証するため、カルテを証拠として裁判所に提出する場合があります。
2. 診断書との違い
カルテと混同されがちな医療記録として診断書があります。診断書も後遺障害の等級認定や、損害賠償請求などで重要な資料ですが、診断書だけでは、ケガの程度や事故との因果関係などを十分に証明できるとは限りません。
診断書は医師が患者の求めに応じて発行する文書であり、主に病名や治療期間、通院日数などが記載されます。
その一方でカルテは、医師が医療行為の過程で随時記録する内部資料であり、診断書には記載されないより詳しい情報や、後から補足できないような経過の記録が残されます。
そのため、診断書だけでは資料として不十分な場合、カルテの入手が必要になるのです。

3. 診療記録との違い
冒頭にも記載した通り、医師法において「診療録」と呼ばれることから、診療録によく似た言葉に診療記録というものがあります。
どちらも広義には患者の診療に関する記録を指しますが、診療記録は診療録に加えて、処方箋、手術記録、看護記録、検査結果、画像データ、紹介状などを含む診療に関するすべての記録のことです。実務的には、医療記録と呼ばれることもあります。
4. カルテの取得方法と注意点
病院など医療機関は、患者からカルテを開示請求された場合、原則としてこれに応じなければならない義務があります。また、患者が未成年の場合は親権者、患者が亡くなった場合は遺族など、一定の条件を満たすケースでは、患者本人以外でも開示請求が認められます。
かつては、カルテの開示請求権や開示義務を巡って争われたこともありましたが、厚生労働省や日本医師会からの指針(ガイドライン)を経て現在では、個人情報保護法を根拠に認められています。
ただし、カルテを取り寄せる際には、いくつか注意すべき点があります。本来、医療機関には一部の例外を除いて診療記録の開示義務がありますが、実際には一部しか開示されなかったり、開示そのものを拒否されたりするケースもいまだにあるようです。
また、カルテには専門的な医学用語が多く使われており、一般の方が内容を正確に理解するのは容易ではありません。
さらに、記載の中には、たとえば「症状は軽度」「事故との因果関係は不明」など、事故との因果関係の立証や後遺障害の等級認定などにおいて、被害者に不利に感じられる表現が使われている場合もあり得ます。しかし、そのような記載があっても、損害賠償請求の場面でも必ず不利になるとは断定できないので、適切に解釈する必要があります。
そのため、医療機関にカルテの開示請求を行う際や、記載内容を交通事故や損害賠償の観点から読み解くには、専門知識を持つ弁護士のサポートが重要になります。
5. 弁護士によるカルテ分析の重要性
交通事故に遭ったものの、被害の程度に見合った後遺障害等級が認定されなかったり、加害者側の保険会社と損害賠償金額を巡って激しく対立したりするケースは少なくありません。
適切な賠償を得るためには、早い段階で弁護士に相談し、対応を任せることが重要です。弁護士であればカルテをスムーズに入手し、記載内容を正確に理解したうえで、加害者側との交渉を通じて正当な賠償金の獲得を目指すことができます。
ただし、弁護士なら誰に相談や依頼をしてもよいわけではありません。交通事故の分野は法律だけでなく、医療に関する知識や保険会社との示談交渉に関する経験など、多岐にわたる知識と経験が不可欠です。
弊事務所には、交通事故に関する知識と経験が豊富な弁護士が揃っており、取扱実績は8,000件を突破しております(2026年1月時点)。皆さまに選ばれた豊富な実績を誇りに、一つひとつのご依頼に対して、心を込めて向き合っております。
医療機関との対応やカルテの分析、保険会社との交渉など、交通事故被害者の方を総合的にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
- 第二十四条
- 関連する用語
- 診療録[しんりょうろく]
用語を探す
キーワードで探す
交通事故に関するキーワードを入力して、該当する用語があるか調べられます。

